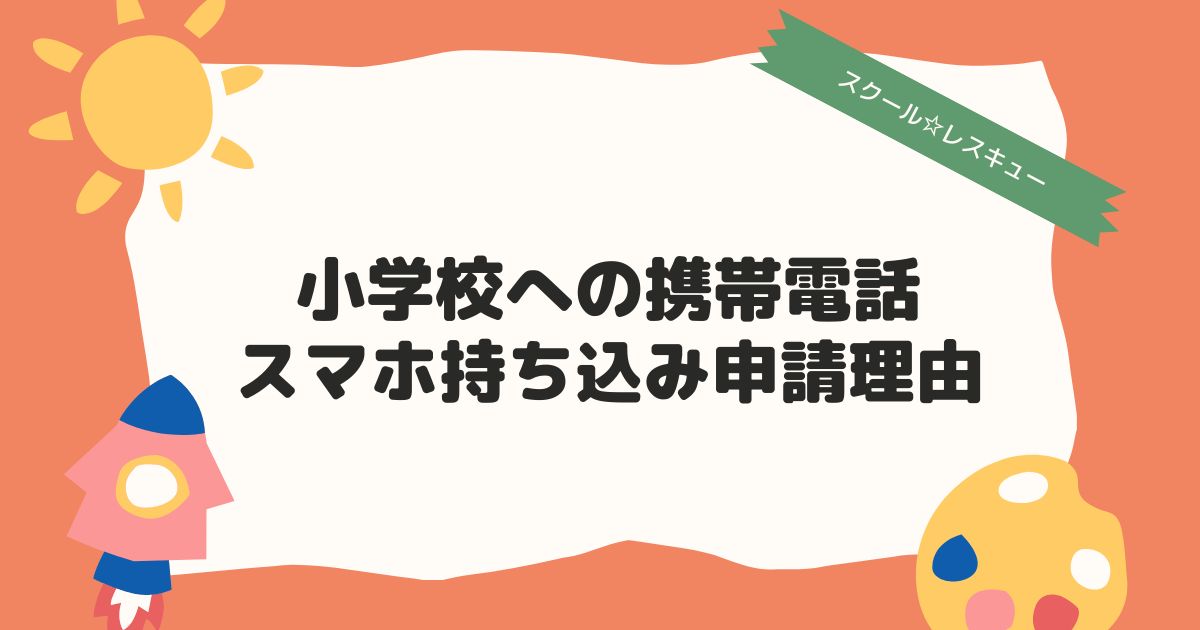小学校への携帯電話・スマホの持ち込みはこれまで原則禁止されていましたが、最近は時代の変化もあり、徐々に容認する学校が増えてきているようです。
もっとも、無制限に認められるわけではなく、学校に持ち込み申請書を提出し、許可をもらうことが条件となっている場合が多いようですね。
そこで今回の記事では、小学校への携帯電話・スマホ持ち込み許可証の申請理由について考察してみました。
申請理由とともに、例文も取り上げているので、ぜひ参考にしてみてください。
なお、小学校へのスマホ持ち込みを想定して書いていますが、中学校・高校などへも応用可能です。
小学校への携帯電話・スマホ持ち込み申請理由
それでは、以下から小学校への携帯電話・スマホ持ち込みの申請理由について見ていきます。
許可が下りやすいと考えられる順に並べていますので、ぜひ参考にしてみてください。
①防災・防犯のため
防災・防犯目的は、文部科学省も「やむを得ない理由」として挙げているものの1つです。
小学校への携帯電話持ち込みは、さまざまなリスクを考えるとやはり原則禁止で、「やむを得ない理由」がある場合に限って許可する、という運用が多いようです。
防災とは、例えば登下校の途中で地震が発生した場合などが想定されています。
携帯電話を持たせていれば、地震が起きてもすぐに子どもと連絡をとり、安否を確認することができるでしょう。
防犯については、例えば子どもを狙ったストーカー被害・連れ去りなどが想定されています。
最近は危機意識が高まっているという時代背景もありますし、また登下校中というのは学校側の監視の及ばない範囲でもあります。
そのため、防災・防犯目的のためなら学校側もある程度は持ち込みを認めざるをえず、これがもっとも許可の下りやすい理由と言って差し支えないでしょう。
昨今、我々の県ではいつ地震が発生してもおかしくない状況ですし、子どもの通学路はハザードマップ上で土砂災害の警戒区域として指定されています。
家から学校まで多少の距離があることを踏まえましても、有事の際はすぐに連絡をとれるよう、子どもには携帯電話を持たせたいと考えています。
学校では一切使用せず、カバンにしまっておくよう指導しますので、どうぞよろしくお願いいたします。
子どもの通学路は見通しが非常に悪く、薄暗い場所も多々あります。
周りに店舗や住宅なども少なく、過去には不審者が目撃されたり、ストーカー被害も発生していると聞きました。
スマホにはGPS機能もついていますし、何かあった時にはすぐに連絡をとれるよう、子どもには携帯電話を持たせたいと考えています。
学校ではカバンから一切出さないようにさせ、もしくは預かっていただいてかまいませんので、持ち込みの許可をいただけますようお願いいたします。
携帯電話の持ち込みが許可されたとしても、
・学校内では使用禁止
という学校も多いようです。
学校で携帯電話をいじる子どもがいると授業などの妨げとなりますし、持っていない子どもとの間でトラブルも生じます。
そのため、許可をもらいやすくするためにも、学校では使用しないよう言い聞かせるとの一文はあってもいいでしょう。
なお、防災・防犯を第一に考えるなら、以下のような見守り機能が充実したキッズスマホを持たせるのがおすすめです。
→みまもり機能が充実したキッズケータイ②通学時間が長くなるため
学校までの距離が遠い、バスや電車などの公共交通機関を利用しなければならない、最寄り駅までの距離が遠い、などの理由から、携帯電話・スマホが必要な場合もあるでしょう。
また、迎えが必要な日などはある程度リアルタイムに子どもとやりとりする必要がありますし、仕事などですぐに迎えに行けない場合は、どこかで待っていてもらう必要もあります。
さらに、通学にバスや電車などを利用する場合は、事故などに巻き込まれる可能性・遅延が発生する可能性もあります。
これらは「緊急連絡手段」という点では①と共通する面があり、許可が下りやすい理由の1つと言っていいでしょう。
貴校へは電車を乗り継いで通わなければなりませんので、何かあった時のために子どもには携帯電話を持たせたいと考えています。
○○線は定期的に遅延も発生しますし、子どもの現在地を把握したり迎えの時間をすり合わせるためにも、携帯電話の所持が必要です。
学校では使用しないよう言い聞かせますので、どうぞよろしくお願いいたします。
家から最寄り駅まで結構な距離があり、帰りが遅くなった日や雨の日などは迎えが必要になります。
私は日中働いており、子どもが帰ってくる時間に必ずしも迎えに行けるとは限りませんので、子どもには携帯電話を持ってもらい、随時連絡をとり合う必要があります。
携帯電話はあくまで連絡手段としての利用に限定し、学校ではカバンから出さないよう言い聞かせますので、どうぞよろしくお願いいたします。
③塾や習い事などに行くため
学校が終わったら直帰せず、そのまま塾や習い事などに行く子どもが最近は増えています。
塾や習い事の終了時刻が明確に決まっているならいいですが、その限りでない場合、終わり次第連絡してもらって、それから迎えに行く必要があります。
また、塾や習い事が終わるころには日も暮れ、辺りが暗くなっていることも多いでしょう。
ただし、塾や習い事の先生から連絡してもらうということも不可能ではないですし、そういう意味では上記の理由よりは少し弱いかもしれません。
このあたりは学校側がどこまで強く禁止したいと考えているかによるので、場合によっては①②の理由に引き付けて書くほうがいいかもしれません。
子どもには学校が終わった後、習い事に行かせていますが、距離的・時間的なことを考えて、学校が終わった後そのまま習い事の教室に向かってもらうようにしています。
習い事が終わるころには辺りも暗くなっていますし、私も仕事の都合上、すぐに迎えに行けるとは限りませんので、子どもには携帯電話を持たせ、適宜連絡をとり合いたいと考えています。
学校では必ず電源を切り、カバンにしまっておくよう指導しますので、どうぞよろしくお願いいたします。
学校へのスマホ持ち込み・リスクやデメリットは?
小学校への携帯電話・スマホの持ち込みが基本的には禁止されていることからもわかる通り、子どもにスマホを持たせることにはやはりリスクやデメリットもあります。
文部科学省の資料にも挙げられていましたが、例えばSNSやネット掲示板を通して犯罪やトラブルに巻き込まれてしまったり、高額課金やアダルトサイトを閲覧するといったリスクもあるでしょう。
また、学校でスマホをいじる子どもがいると、スマホを持っていない子どもとの間で格差が生じてしまい、トラブルやいじめの原因にもなりかねません。
子どもにスマホを持たせる場合でも、こうしたリスクにはしっかり対処する必要がありそうですね。
→みまもり機能が充実したキッズケータイ